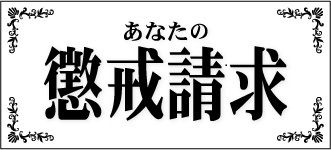
懲戒請求の議決書が届きました。杉山程彦弁護士の4回目の処分の議決書です。
弁護士の処分で相手方への攻撃の方法、言論が不当であると処分されても、依頼者のためによく頑張ったと許せる場合もありますが、処分の中で依頼者に対して迷惑をかけた行為の処分については、たとえ戒告であったとしても当事者は許せるものではありません。
今回の懲戒請求者は、親権問題の団体の代表を務める方の依頼でした。この問題では被懲戒者は常にXに投稿し、親権問題の第一人者であるとの評価もあります。
どのような裁判であったかは詳しくいうと個人が特定されますので書きませんが、離婚問題の当事者のみならず世間が大きな関心を寄せた裁判でした。訴訟の相手方はあの有名な女性弁護士らだったのですから、慎重に裁判を進めてもらいたかったといわざるを得ません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』2026年4月号に処分要旨が掲載されます。
神弁発懲第111号
事務所 横須賀市若松町3-4 山田ビル プレミア法律事務所
対象弁護士 杉山 程彦 (登録番号37300)
本会は上記の者に対する2024年(懲) 第10号事案について、懲戒委員会の議決に基づき、次のとおり懲戒する。
主 文
対象弁護士 杉山 程彦 を戒告とする。
理 由
本会は、 標記事案について懲戒委員会が別紙議決書のとおり議決したので、 弁護士法第56条に基づき主文のとおり懲戒する。
2025年10月20日 神奈川県弁護士会 会長 畑中隆
懲戒請求者 親権問題の団体の代表者を務める個人元依頼者
上記代理人弁護士 太田 真也弁護士(東京)神田のカメさん法律事務所
対象弁護士 杉山 程彦 (登録番号37300)プレミア法律事務所
上記対象弁護士に対する懲戒請求事案につき審査した結果、次のとおり議決する。
主 文
対象弁護士杉山程彦を戒告することを相当と認める。
第1 懲戒請求事由の要旨
1 懲戒請求事由1
理由
懲戒請求者は、懲戒請求者が被告とされた東京地裁立川支部令和4年(ワ)第 3134号損害賠償請求事件(以下「本件訴訟」という。)について、2023年(令和5年) 2月19日に対象弁護士に訴訟代理人となることを依頼し、対象弁護士はこれを受諾したが、 その際、対象弁護士は懲戒請求者に対し来る2023年(令和5年) 3月1日に予定されていた本件訴訟の第2回口頭弁論期日を第1回口頭弁論期日であると誤解し、懲戒請求者が本人自身で訴状の請求原因に対して認否反論する準備書面を提出するのをやめさせた。
懲戒請求事由 2
対象弁護士は、前記誤解に基づき、 本件訴訟の第2回口頭弁論期日までに、訴訟代理人として訴状の請求原因に対して認否反論する準備書面も提出せず、訴訟 委任状も提出せず、上記期日に裁判所に出頭することもしなかった。
3 以上の結果、 2023年(令和5年) 3月10日(判決期日)に、懲戒請求者に対し請求(金330万円の支払いを求めるもの)を全部認容する判決の言い渡しがなされた。 よって対象弁護士の上記行為 (依頼者に対する説明指示及び訴訟対応) は、弁護士としての基本的注意義務を怠ったもので、弁護士法第56条 1項の「品位を失うべき非行」 にあたる
第2 対象弁護士の弁明の要旨
1 懲戒請求事由に関する事実関係はおおむね認める。
2 期日経過を誤解した経緯は以下のとおりであるが、反省している。
即ち、対象弁護士は、懲戒請求者から本件訴訟の依頼と並行して別件訴訟の依頼も受けた。 別件訴訟の依頼も本件訴訟と同じく名誉棄損を理由とする損害賠償 請求を提起された被告(懲戒請求者が代表者を務める団体)からの依頼であった。
本件訴訟も別件訴訟も、子の監護に関する夫婦間の対立的主張が争点となる離婚事件(以下「別件離婚事件」という。)に関して、被告側がインターネットに掲載した記事の内容が名誉棄損にあたるとの主張がなされた事案であったところ、 対象弁護士は、別件離婚事件の記録を閲覧し、その内容を検討してから自身が作成した書面を提出するのがよいと考えた。 そして、懲戒請求者から答弁書は提出済であると聞いたので、第1回期日は本人も欠席して答弁書の擬制陳述で済ませ、第2回期日前に裁判所に訴訟代理人が受任した旨を報告し、しかるべき書面を提出する方針を立て、懲戒請求者に伝えた。
ところが、対象弁護士は、2023年 3月14日に懲戒請求者から本件訴訟の判決が届いたとの連絡を受け、 2023年3月1日の期日が第1回口頭弁論期日ではなく、 請求原因に対する認否反論を記載した準備書面の提出が必要とされた期日であったことを知った。 期日の経過について依頼者の話を聞いただけで、十分に確認しなかった点は反省している。
3 本件訴訟の第1審判決が出された後、対象弁護士は、以下のとおりそれなりの誠意をもって懲戒請求者に対応した。
(1) 控訴審の対応
対象弁護士は、本件訴訟の判決を知った後、本件訴訟の控訴審の訴訟代理人 として控訴状 (2023年3月14日付) を作成して裁判所に提出した。 但し、その後の同年3月26日に対象弁護士は懲戒請求者から本件訴訟及び別件訴訟の訴訟代理人を解任され、その後の訴訟行為はできなくなった。
(2)着手金の返還
対象弁護士は、懲戒請求者に対し、 本件訴訟及び別件訴訟に関して受領して いた着手金(本件訴訟25万円、 別件訴訟 25万円) を全額返金した。
(3)損害賠償請求への対応
対象弁護士は、2023年3月以降、懲戒請求者から本件訴訟における訴訟 代理業務の懈怠に関して損賠賠償請求を受けるようになったが、これについても、対象弁護士が弁護士賠責任保険の保険金を請求し、受領した保険金を全額 を懲戒請求者に全額支払うとの合意書の作成を進めたりするなどして誠意をもって対応してきた。その訴訟外で和解協議は整わず、その後、懲戒請求者及び 懲戒請求者が代表を務める団体は 対象弁護士に対し本件訴訟や別件訴訟における対象弁護士の対応に過失があるなどとして計金540万円の支払いを求 める損害賠償請求訴訟を提起してきた (東京地裁令和6年(ワ) 第100号損害賠償請求事件)。 対象弁護士は、当該訴訟における和解協議にも誠意をもっ て臨んでいる。
4 懲戒請求の不当性
懲戒請求者は、2023年5月、 対象弁護士に対し、示談金として330万円 あるいは本件訴訟の最終的な敗訴額に50万円を加えた額を支払うよう要求し、その提案に応じない場合には、 対象弁護士を懲戒請求するとの通告をしてきた。 対象弁護士は提案を拒絶したところ、対象弁護士に540万円の支払いを求める前記損賠賠償請求訴訟が提起された。
しかるに、本件訴訟の控訴審で成立した和 解で、懲戒請求者が支払うべき金員は40万円に過ぎなかった。 懲戒請求者は自 身が被った実際の損害額を大きく超える不当な過大請求をしてきており、懲戒請求者はそのような請求を実現するために懲戒請求制度を利用しているとしか評価できない。 このような懲戒請求がなされるなら 弁護士がミスをしたことで法外な示談をせざるを得なくなる。
本件の懲戒請求は恐喝行為というべき濫用的な不当な請求であって認められるべきではない。
第3 証拠
別紙証拠目録記載のとおり (省く)
1 認定した事実
(1) 懲戒請求者を被告とする損害賠償請求訴訟(名誉棄損を理由とするもので請求金額は330万円) (本件訴訟) が提起され (2022年11月22日)、 東京地裁立川支部に係属した(東京地裁立川支部令和4年 (ワ)第3134号) (甲5,甲7)。
(2) 本件訴訟の第1回口頭弁論期日は2023年 (令和5年) 1月18日と指定された(甲5)。
(3) 懲戒請求者は、第1回口頭弁論期日前に、請求棄却を求めるだけの答弁書(請 求の原因に対する認否反論の記載はされていないもの)を提出した(甲7)。
(4)第1回口頭弁論期日には、訴状陳述、答弁書の擬制陳述の手続がなされ、 第2回口頭弁論期日が2023年 (令和5年)3月1日に指定された(甲7)。
(5) 懲戒請求者は、2023年(令和5年)2月19日、 対象弁護士に対し本件訴訟の訴訟代理人となることを依頼し 対象弁護士はこれを受任した(口頭契約)(対象弁護士答弁書自認)。
(6) 上記受任の際、 対象弁護士は懲戒請求者に対し、来る2023年(令和5年) 3月1日に予定されていた本件訴訟の第2回口頭弁論期日を第1回口頭弁論期 日であると誤解し、懲戒請求者が本人自身で訴状の請求原因に対して認否反論 する準備書面は提出しないでおくよう指示した (対象弁護士自認)。
(7) 対象弁護士は、2023年2月23日、 懲戒請求者に委任契約書、 委任状をメールで送信し、 返送するよう指示した (甲2)。
(8) 懲戒請求者は、2023年(令和5年)年3月1日の第2回口頭弁論期日に欠席し、請求原因に対する認否反論をする準備書面も提出しなかった(甲7).
(9) 対象弁護士も、前記期日までに訴訟代理人として訴状の請求原因に対して 認否反論する準備書面も提出せず、裁判所に訴訟委任状も提出せず、上記期日に出頭することもしなかった (対象弁護士答弁書自認)。
(10) 対象弁護士は、 上記期日経過後、後記の判決期日までの間に、懲戒請求者に対し、本件訴訟の次回期日がいつであるかの確認する問合せをしなかった(当委員会における2025年6月25日実施対象弁護士審査期日における対象弁護士の供述)。
(11)懲戒請求者は、2023年3月7日、 委任契約書に署名押印のうえ返送し、 同日、対象弁護士に着手金として25万円を振込送金した (甲3 甲4)。
(12)2023年 (令和5年)3月10日、 上記訴訟の第3回口頭弁論期日に、 原告の請求を全部認容する判決の言渡しがなされた(甲7)。
(13) 対象弁護士は、本件訴訟の判決を知った後、懲戒請求者からの依頼を受けて、本件訴訟の控訴審の訴訟代理人となり、 控訴状 (2023年3月14日付)を作成して裁判所に提出した。 但し、その後の同年3月26日に対象弁護士は懲戒請求者から本件訴訟及び別件訴訟の訴訟代理人を解任された (乙3)。
(14) 対象弁護士は、懲戒請求者に対し、本件訴訟及び別件訴訟に関して受領していた着手金(本件訴訟25万円、 別件訴訟25万円) を全額返金した (乙8)。
(15) 対象弁護士は、2023年3月以降、懲戒請求者らから本件訴訟における訴訟代理業務の懈怠に関して損賠償請求を受けるようになった。これに対し、対象弁護士は、弁護士賠償責任保険の保険金を請求し、受領した保険金全額を懲戒請求者に全額支払うとの提案し、その旨の合意書(案)の作成を勧めたりするなどして対応してきた(乙9、10、11)。
(16) 上記の訴訟外で和解協議は整わず、 その後、懲戒請求者及び懲戒請求者が代表を務める団体は、 対象弁護士に対し、本件訴訟や別件訴訟における対象弁護 士の対応に過失があるなどとして計金540万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起してきた(東京地裁令和6年(ワ)第100号損害賠償請求事件) (乙13)。 当該訴訟においては和解協議も進められていたが、2025年5月24日の時点で和解は成立していない (対象弁護士による2025年5月24日付期日延期申立書)。
対象弁護士は、懲戒請求事由1及び同2の事実をおおむね認めており、当委員会も対象弁護士による上記自認の答弁及びその他の関連証拠に照らして、これを認める。
弁護士職務基本規程第29条1項は、 「依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない」と定め、同規程第37条2項は「弁護士は、事件の処理にあたり、 必要な事実関係の調査を行うよう努める。」と定めるところ、 対象弁護士が、本件訴訟の第2回口頭弁論期日 (2023年3月1日)を第1回期日であると軽信し、 かつ、上記期日経過後もすみやかに上記期日の次回期日の確認もせず、懲戒請求者に不適切な指示説明をし、自らも必要な訴訟行為をしなかったことにより、 被告とされた懲戒請求者に請求の全部認容の判決を受けるという不利益をもたらしたことは、 係属中の訴訟事件の依頼を受けた弁護士として、上記各基本規程により示された弁護士の基本的な注意義務に違反したもので、その違反の程度も大き いと言わなければならない。
なるほど、対象弁護士は、上記事態を招いた自身の軽率さを反省し、受領した着手金を懲戒請求者に全額返還し、 また、 対象弁護士の過失により損害を被ったとしてその損害の賠償を請求してきた懲戒請求者に対しても、訴訟外の段階で示談を進めたり、訴訟となった後もしかるべく和解を成 立させようと努めている姿勢も伺え、懲戒請求者の被った不利益をできるだけ回復させようとの事後的対応をしている事実も認められる。 しかしながら、対象弁護士は、 過去5年間に、当会より、各種の弁護士職務基本規程に違反したものとして計3回の懲戒処分 (戒告2回、 業務停止1月1回) を受けている。
以上のように、 対象弁護士は過去5年間に本件も含めた弁護士職務基本規程の 行規範の違反を繰り返している点に鑑みると、本件において対象弁護士が反省し、懲戒請求者の被害回復に努めようとしている等の対象弁護士に有利な事情を最大限考慮しても、対象弁護士の行為は弁護士法第56条1項の「品位を失うべき非 行」にあたり、 戒告の限度で懲戒処分に処することは免れないと当委員会は判断した。
なお、対象弁護士は、 懲戒請求者は自身が被った実際の損害額を大きく超える 不当な過大請求をしてきており、懲戒請求者はそのような不当な請求を実現するために懲戒請求制度を利用しているのであり、このような懲戒請求がなされるな ら、弁護士がミスをしたことで法外な示談をせざるを得なくなるので 本件のような懲戒請求は濫用的な不当な請求であって認められるべきではない旨の主張をする。
しかしながら、 懲戒請求は弁護士会の自治的権能の一つとしての懲戒権の発動を促す申立であり、懲戒権発動のいわば端緒でしかないと位置付けられていることから(日本弁護士連合会 「弁護士懲戒手続の研究と実務」 64頁)、懲戒請求を申立てた懲戒請求者の主観的な意図に本来の目的外の他事考慮が含まれていたとしても、それをもって懲戒委員会の事実認定と判断が左右されるものではないと解される。
よって、主文のとおり議決する。
2025年8月20日
2024年(懲)第10号
神奈川県弁護士会懲戒委員会委員長 氏名 印

